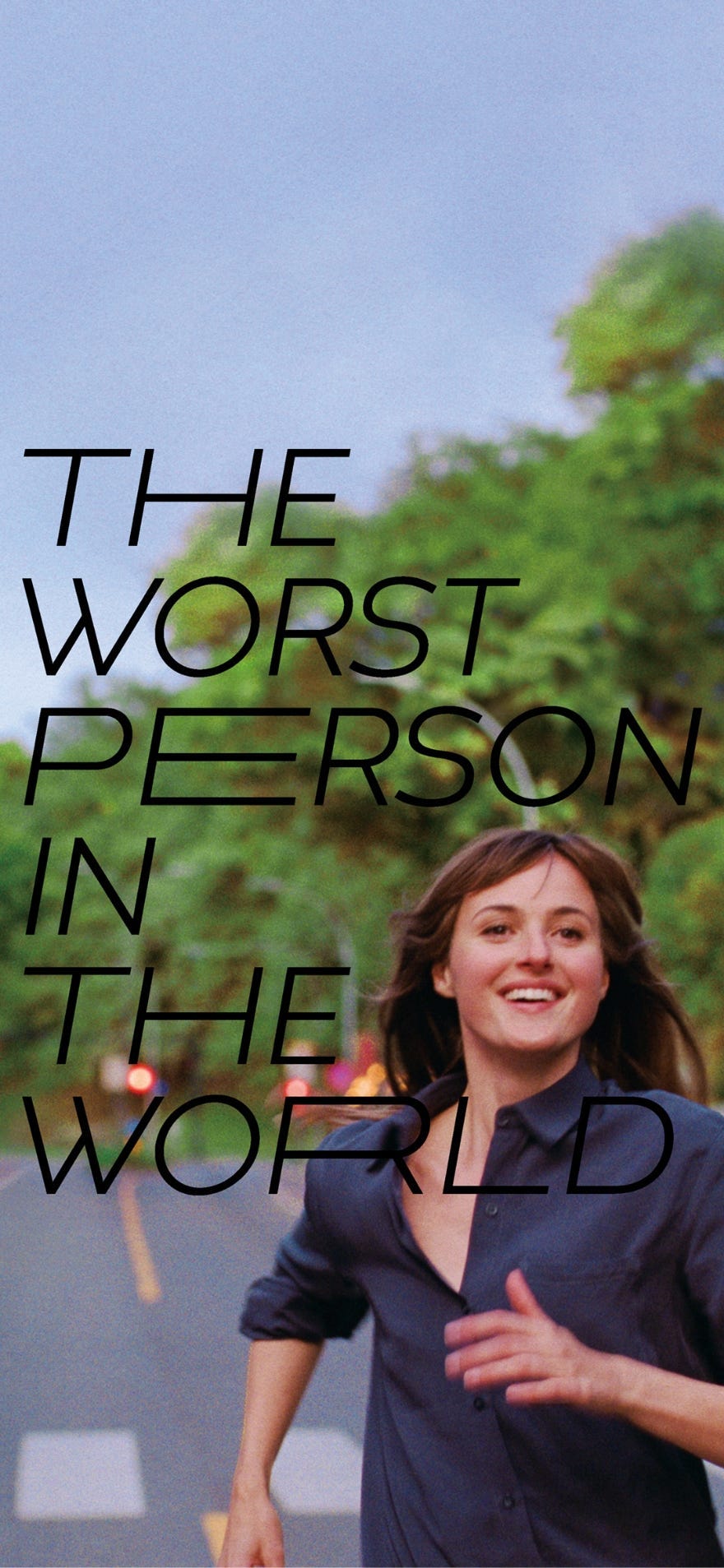大人になれば宿題をやらなくて済むし、定期的にやってくるテストの類もなくなると思っていたが、実際に大人になってみると、毎日毎日終わらない宿題とひっきりなしにやってくるテスト(基本的に抜き打ち)になるだけで、むしろ状況は悪化している。とはいえ子どもの頃よりは「ちゃんとやらなくていい」ということを覚え(理解し?)、生きやすさのようなもの(QOL?)は上がっているような気はする。
毎月1本=1章を書き上げるペースでやっている、つまりある種の宿題的な感じでやっている原稿を、今月は1文字も書いていない。夏休みの宿題にまったく手をつけずに8月の終わりを迎えるのは人生ではじめてである。なぜこんなにも罪悪感がないのだろうか。わたしはもう優等生ではない。わたしは最悪。
そう、『わたしは最悪。』である。先週のお休みにやっと観に行けた待望の1作。本当はもう少し前に行く予定だったのだけど心が折れて(なにが原因で折れたのかはもうわからない)、諦めていたのだけど、やっぱり観に行くべきな気がして(こちらも理由はわからない)劇場検索をしたところ、柏のキネマ旬報シアターでまだやっていた(9/9まで)。
HPに載っているあらすじはこんな感じ。
学生時代は成績優秀で、アート系の才能や文才もあるのに、「これしかない!」という決定的な道が見つからず、いまだ人生の脇役のような気分のユリヤ。そんな彼女にグラフィックノベル作家として成功した年上の恋人アクセルは、妻や母といったポジションをすすめてくる。ある夜、招待されていないパーティに紛れ込んだユリヤは、若くて魅力的なアイヴィンに出会う。新たな恋の勢いに乗って、ユリヤは今度こそ自分の人生の主役の座をつかもうとするのだが──。
で、上の壁紙のシーンが予告編ではフィーチャーされているうえに、主人公(ユリヤ)以外の人間は止まっているため、予告編だけ見るとかなりSF要素強めな感じがする。時かけ、的な?みたいなことを勝手にイメージしてしまう類の(主人公が定期的に時を止めるイメージ)。でも文字情報のあらすじを読むとまったくそんな感じはしないのだが、5月末に観た『帰らない日曜日』の前に流れてた予告動画だけで観ることを決めて、そのあとあえて情報を入れずにいたので、あれ?みんな止まらねえな?とかちょっとばかし思いながら最初の30分くらいは観ていた。
が、この時が止まる場面は一度だけで、しかし当然のようにキーファクターになっているのだけど、個人的にはこのある意味スペクタクルな(?)仕掛けが仮になかったとしても、感慨深いストーリーになっていたと思う、というか、実際、観終わったときにはこの場面は「要素のひとつでしかない」という印象になっていた(この場面自体の素晴らしさはもう本当に素晴らしいんですが、映画評スキルがなくてちょっとうまく言語化できないのでアレがアレ的なアレでご勘弁)。
ということでなにかまとまったテーマ=軸のある評になる気がしないので雑多に気になったところを摘み書きしていくことにする。記憶を頼りに書くので正確ではない情報(とそれに基づいた意見)がある可能性は非常に高い。このあたり、本はすぐに確認できるから安心感がある。ネタバレはもちろんする。
基本的には主人公ユリヤの「成長譚」という物語形式なのだけど、成長する、あるいは他者に影響を与えられる(=成長する)/与える(=成長のきっかけになる)、という構図が登場人物間で相互的に生まれている感じがあって、そこが個人的にはグッドだった。何者かになりたいがなにをどうすればいいかわからずモヤモヤしている若者(という典型的主人公像)が、可能性(=〜かも、もしかして〜)を感じとったものや人に挑戦し、あるいは憧れ、でもやっぱりそれは「〜かも、もしかして〜」でしかなくて、どうもしっくりこない……まま月日が流れていく(というこれまた典型的流れ)。これが、どうもユリヤのみならずアクセルやアイヴィンもこの模索の中にいるのではないか?というように考えると、この物語の流れと結末がグッとくるのである。
ユリヤは当初「子どもがほしいかどうかわからない(どちらかといえばほしくない)」という状態にあって、そのことでアクセルとも意見が合わない。合わないままも数年(おそらく。この映画は全12章のチャプターごとにわかれていてこの仕掛けもまた素晴らしいのだけど、その間の時間経過がどれくらいなのかははっきりと描かれない)ともに過ごし、それだけが理由ではないけれど、最終的には別れることになる。
そのあとユリヤはアイヴィンと付き合い出し、なんやかんやでうまくいってる感じになる(これはアクセルとのときもそうだったのではないか、少なくとも彼女の中では)。が、妊娠していることがわかり、しかもアイヴィンもまた子どもはほしくない派なのでなかなか言い出せない。というタイミングでアクセルが末期癌であることを知り、見舞いに行く、というより話を聞いてほしくて行ったのかもしれない。そう、ユリヤはおそらく非常に自分勝手なのだけど、でもそれがいいな、とも思った。
子どもが欲しかったけどできないまま破局し、しかも末期癌で死期がわかってしまっているアクセルの元に、ユリヤが妊娠の相談(むしろ報告と言ってよい)をしに行く、しかもアイヴィンにするよりも先に。という非常に皮肉な構図になっている(子どもはいらないという点でもバッチリだったアイヴィンとの間に、というのもまた同様に)。
ユリヤはアクセルとの日々からアイヴィンとの日々にかけて、産みたくないから産んでもいいのかもしれない、に気持ちが変わっていたのかもしれない。相談をしに行くというのはそういうことだ。アクセルのユリヤに対する「作用」が垣間見える。となるとアクセルもまたユリヤに「作用」を受けているはずだ。残念ながらこの点の描写は確認できなかったので、やっぱりもう一回観たい。ということでアクセルについての印象的な場面を代わりに言及しておくと、病室でユリヤに対して「君に自信を持たせてあげたかったんだ」というようなことを言うのだけど、これが非常に多面的・多層的に捉えられる台詞だと感じて、みんな!これどう思った!?って聞きたくなる。
で、最終的にユリヤは流産し(これがまたアクセルの死の直後というのがまた……)、そのちょっと前にアイヴィンとも「距離を置く」感じになっていて、そのあとチャプターが変わってどうやらアイヴィンとは破局していることがわかる……というこの循環?がうまいなあ……とため息をついてしまった。
しかも最終章では写真家としてキャリアを築いていってる(ように見える)ユリヤがいて、撮影後の宣材用スナップ写真を撮った女優を外で待っていた子連れの男がどうやらアイヴィンであり、という結末もやってくるのだから恐ろしい。そのおそらく若手の女優は別れのシーンを撮影していて、最初のテイクでは「うまく泣けずに」、監督から「涙だ」みたいな(ある種の安直な要求)を受け、仕方なくそれを採用して「素晴らしい!」と言われ、そのあと納得のいかないままユリヤの元で撮影をする。「今の気持ちのままの表情で」みたいなことを言うユリヤは、おそらく女優の「これじゃない(でもなにが正解かはわからない)」という心情を「知っている」のだろう。それはかつての(あるいは今もまだいる)自分だったからだ。なんならアイヴィン(年上)×年下の女性という構図はユリヤとアクセルのそれだし、これもまた循環、いや螺旋構造な気もする。完全に同じ構造を繰り返しているのではなくて、お互いに作用し合ったうえでの循環なので、螺旋っぽいイメージになる。そうだね、螺旋だね。
あとは、後悔というテーマ。予告編にもあるけど、ユリヤもアクセルも「絶対に後悔する」ことがわかったうえで破局している。妊娠がわかったユリヤはなんでアクセルとではなかったのか……と思ったかもしれないし、アクセルはアクセルで「無理に欲しがらなければ」という後悔があったかもしれない。あと、アクセル危篤の知らせを受けてもユリヤは病室に行かない、というのがまたなんというか……なんだかんだで大切な人なんだけど、でももう他人なんだ、わたしは自分の人生を生きるのだ、みたいな感覚だと思うんだけど、そうやって距離を置いた=決別したことを後悔するときが来るんだろうな、というのを思うとやはりしんみりする。若気の至りのひとつか。過去の恋人の連絡先を強い気持ちで消してしまうのが若者だけど、歳をとってくると連絡先くらい残しておいてもよかったのにな、だっていま幸せに過ごしているのかどうかもわからないのはなにか違うんじゃないか?みたいなことを思ってしまうのは個人的な経験が強すぎるだろうか。いまが幸せだけど、だからこそ感じる後悔みたいなものが人にはあるような気がしていて、そこをうまくついているのではないかと思った。ifの物語。そういう意味ではこの映画も時かけみたいなものなのかもしれない。
パンフレットとかにも書いてあるけど、フェミニズムというテーマはナチュラルに通底するテーマになっていると感じた。前面に出す訳ではないし、かといって避けるわけでもない、ナチュラルさ。生活の中にあるものなんだからそれを描かないのは逆に不自然でしょ?みたいな感覚。フェミニズム映画ではないが、フェミニズム的であり、ゆえにフェミニズムの視点で鑑賞・批評することが可能/自然な作品になっている。ノルウェーの女性が感じている「男女平等が進んでいるからこそ女性の自立や活躍が当然視されることからくる成功へのプレッシャー」という生きにくさもまた、この物語の通底するテーマである。そのあたりの観点・視点から批評するともっと面白くなるはず。
あと、映画冒頭のスタッフクレジットみたいなものが、確か青黄赤の3色を背景としていて、この色が結構印象的だったのでなにか後々あるかもな?と思っていたらやっぱり出てきたので意味があるのかもしれない。出てきた場面は死の直前?にアクセルが子どもの頃に住んでいた家にユリヤを連れていって、色々と思い出を話す(ユリヤはその様子を写真に撮っている)場面。漫画家になったアクセルはよくこの色付き窓を通して外を見て、世界を想像/創造していた、みたいなことを言っていた。やはり大事な意味、あるいは象徴が付与されているに違いない。ユリヤの写真家としてのキャリアはこれがきっかけだったかもしれないし(ユリヤは学生時代に写真の才能があるかも!となっていて、その縁でアクセルと出会っているが、そのあとは写真を一切撮っていなかったのも、良き構図である)。
ほかにも気になった点があった気がするが、思い出せないので終わりにする。
ここのところ読んでいた本がデボラ・レヴィ『ホットミルク』で、これがどうも『わたしは最悪。』と通底するなにかを持っているような気がしていて、絡めて考えてみたいな、という思いも芽生えている。とにもかくにも、もう一度、いや何度も観たいのである。円盤が出たら、あるいはアップルTVとかで配信されたらすぐに買う。レンタルではなく買う。アマプラ見放題でもない。だから買えるもので出してくれ。頼むぞ制作・配信元。
そのためにもわたしは宿題をちゃんとやって「いいこ」であらねばならない。なぜ提出必須の課題をやらずに希望者のみの自由研究(推敲なし)をやっているのだろうか。この時間(だいたい2時間)で本来の原稿を書いていればそこそこの文量になっていたのではないか。来月からがんばります。でもわたしは「がんばってない子」のところにもサンタさんがやってくることを知っている、というかそうであるべきだと思っているので、がんばらなくてもいいことを知っているし、それが許されてほしいとも思っている。というような大人、あるいはわたしは最悪なのだろうか。この問いに対する答えを見つけるのもまた宿題です。冒頭のタイトルとなにか掛けてあるようで掛けてないような、でもやっぱり掛けてある気がしちゃう1文で締めます。これの文脈(=掛かっているとする根拠)を考えるのもまた宿題です。