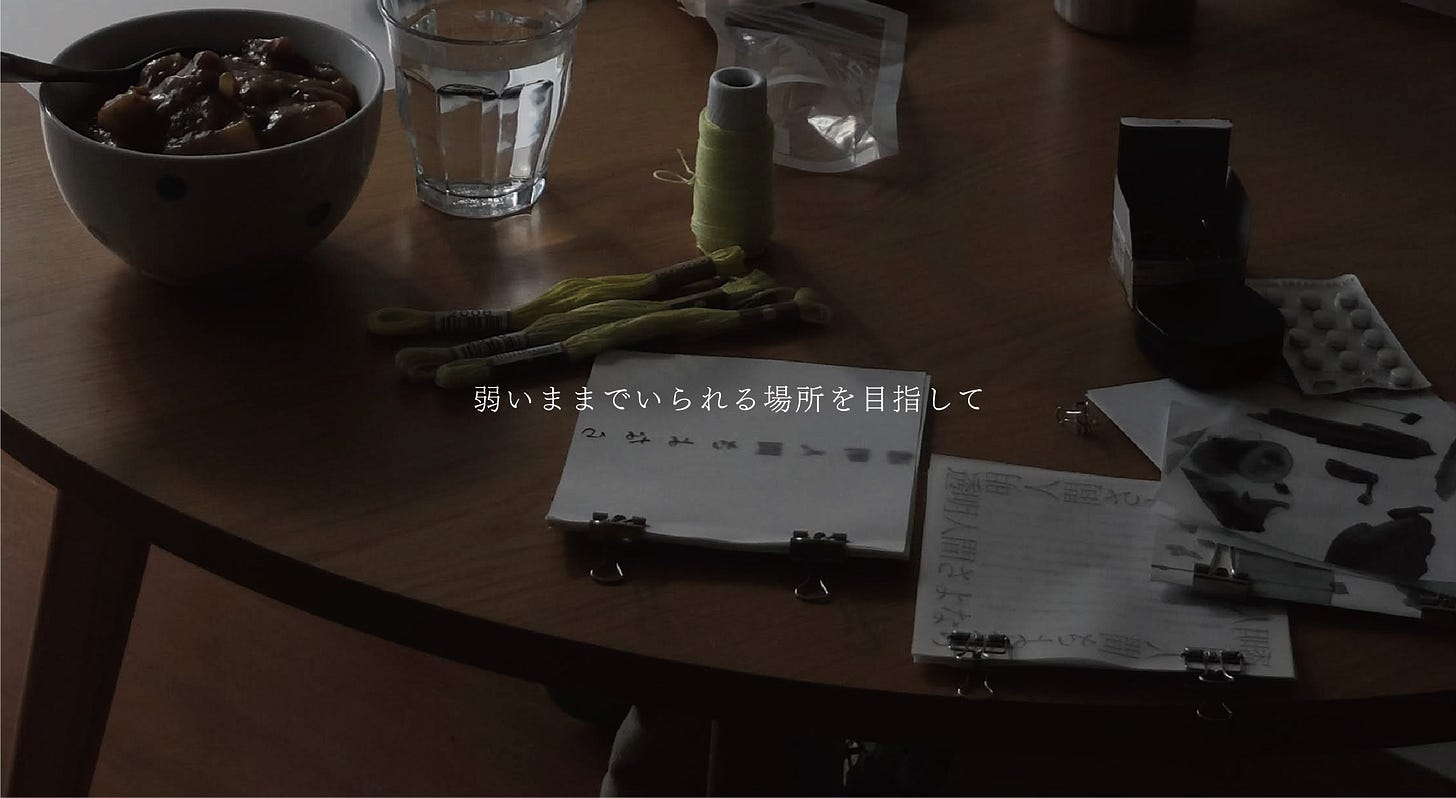弱いままでいられる場所を目指して #09/本屋メガホン
たねをまくこと
社会的マイノリティについて書かれた本をメインに取り扱い、「小さな声を大きく届ける」ことを目指す新刊書店「本屋メガホン」を運営する著者による雑記。本屋を運営しながら考えたこと、自身もマイノリティとして生きる中で感じたことなどを思いつくままに書いていきます。
※後半部分にて、自死に関する話題に触れます。
生活の拠点を岐阜から関西に移すことになり、2025年4月末にて岐阜での店舗営業は終了した。しばらくはオンラインストアとイベント出店をメインに本の販売を行い、ZINEの制作はこれまで通り継続しつつ、本連載の第7回で書いたように柔軟にあり方を模索しながら、何にでもなれる状態をしばらくは楽しもうと思っている。営業終了までの数ヶ月間、遠方から目当てに来てくれる人がいたり、何度かお店に来てくれていた人と少し長く話したりする中で、この2年間を振り返って、場所を持つことの意義や、本屋という営みを通してできること/できないことについて色々と考えるきっかけをもらうことができた。今回は、岐阜での店舗営業を終えるまでに考えたことや気づいたことについて書いてみたい。
* * *
以前出店したイベントで、本屋メガホンのZINEを読んだことが自分でもZINEをつくるきっかけになったと話してくれた人がいて、とても嬉しかった。そのZINEは『生活と怒号』というタイトルで、まさに「もっとみんな軽率にZINEをつくったり自分のことについて書いたりしようよ」という内容のものだったので、自分の声がZINEを通して誰かに届いたことを実感できた体験だった。また別のある人からは、本屋メガホンとして最初につくったZINE『透明人間さよなら』を読んで、パーソナルな語りをZINEという形で他者にひらくことに共感し、自分でもZINEをつくる励みになったと連絡をもらって、これもまさにそういう意図でつくったものだったので、こちらの意図に近い形で受け取ってもらえて嬉しかったことを覚えている。
ある日の店舗営業では、何回かお店に来てくれていたお客さんが、「自分のままでいられる居心地のいい空間だったから、なくなるのは寂しい」「自分もいつかこういうことをやってみたい」と話してくれて、内心嬉しさで泣きそうになりながらお会計をしたことがあった。居心地の良さを感じてくれたことは、確かにその人の中に感覚として残るものだと思うので、それもまた一つのきっかけではあるだろうし、そうやって体験や体感として何かを持ち帰ってもらえることは、場所を構えて持つことの大きな利点だと思う。また、以前名古屋で友人と企画して開催した「本読みデモ」を真似して自分でもやってみたとSNSに投稿している人がいて、自分の起こした行動が遠く離れた誰かの行動を後押しすることもあるということを実感できた。
これらの出来事は、本屋メガホンとして意図してつくったものや意図せず醸し出された何かが、各々の回路を通して受け取られ、それが受け取られた結果その人に何かしらの影響を与えたということを、自分が偶然観測できた瞬間だと思う。そう考えると、自分が本屋メガホンの活動を通してやってきた/やりたかったのは「たねをまくこと」に尽きるなと思う。固定の場所を持つこともそうだし、仕入れた本が誰かの手に取られるまで待つことも、自分でZINEをつくって売ることも、セーファースペースを目指すことも全て、抵抗や連帯や言語化やその他何かしらのステップにつなげるための「たねをまくこと」なのだと思う。その「たね」は、ある人は具体的な言葉や指針や制作物として受け取るかもしれないし、ある人はその場の雰囲気や「居心地の良さ」として受け取るかもしれないし、またある人は自分が想像もしていなかったような思いがけない何かとして受け取るかもしれない。受け取られた「たね」は具体的な行動として芽を出すかもしれないし、もっと深い層で静かに根を張り続けるかもしれない。どちらにせよ、私には「たねをまくこと」までしかできなくて、受け取られ方や受け取られた先については干渉できない。その潔さというか、(影響を「与えてしまえる」立場であることに対しては一定の責任を引き受けつつ)ある種無責任で野放図な、世界や社会や他者への干渉の仕方が本屋という営みの本質にあるものなのかもしれない。
「たねをまく」という行為そのものやそれを受け取った結果なされるアクションは、同質的なコミュニティを特定の場所に形成したり、誰かと誰かがつながったりするようなあり方では必ずしもなくて、ある種「勝手に」「バラバラに」「脈絡なく突然」湧き起こるもので、直接的な対話や交流を必要とせずに、「つながらないままともにある」ことができる点が好ましいなと思う。本屋メガホンの活動を始めてからずっと、「店主/客」や「売る/買う」といった、勾配が生じやすい関係性をいかにフラットにできるかを考えたいと思っていて、そういう意味でも、「たねをまくこと」という視点で色々な活動を俯瞰してみると、より柔軟なあり方やフラットな関係性の築き方について考えるきっかけにもなるような気がする。店舗営業の終了に伴って営業形態は変化していくが、それと同時に、色々な「たねのまき方」についても模索してみたい。
* * *
約2年間の店舗営業の中で、本屋にはできないことについても同様に考える瞬間があった。2023年夏頃にryuchellの自死のニュースがあった時に、「死にたくなったら本屋に来てほしい」という内容のポストをSNSに投稿する本屋がいて、もちろんそれは善意かつ本心なのだろうが、僕にはある種の「販促」でもあるように思えて、とても虚しくなったことを今でも鮮明に覚えている。その時、本屋という営みは本質的に「死にたいという気持ちを直接なくすことはできない」と思った。死にたい気持ちに「寄り添う」ことはできても、それを根本的に解決することはできない。解決することが果たして本当に「正しい」ことなのかどうか、という議論はあるとして、そこには確かに本屋という営みの限界があることを痛感したのだった。
こうやって安全圏から、今の自分にはない「死にたい気持ち」について「寄り添う」とか「なくす」とか書くことも綺麗事を言っているようで虚しいな、と思うのだけれど、基本的に「いいもの」として扱われやすい独立系書店だからこそ、あるいは、社会的マイノリティについて書かれた本をメインに扱うというコンセプトを掲げているからこそ、本屋という営みにも限界があることをどこかにはっきりと書いておく必要があると思った。本屋はただ本を売るための営利活動でしかないから、治療もカウンセリングもできない。死にたい気持ちの隣にただ座っていることはできても、それを根本的に取り除くことはできない。本屋を運営することも、セーファースペースを目指すことも、そうやって限界を意識し続けることでしか持続可能で本質的な議論には辿り着けないような気がする。
でも、それでも、やはり自分には「たねをまき続けること」しかできないし、誰かが根気強く「たねをまくこと」でしか掬いきれない何かもある、と思いたい。そう考えると、「たねをまく」という行為は、その限界と可能性を両極にではなく、限りなく表裏一体に近い位相にあるのものとして併せ持ったものなのかもしれない。常に限界がすぐそこにあることを意識しながら、それでも、この世界は信用にたるものであると祈り続け、たねをまき続けること。限りなく近い位相にあるからこそ、限界がそのまま可能性に転じることを(たとえ表層的で抽象的な言葉遊びだとしても)信じ切ること。本屋メガホンとしての活動を、小さな「たね」がその小ささや密やかさを保ったまま、大きなうねりとなることを長いスパンで待ち続ける過程だと位置付けてみると、今の政治や社会へのやるせなさも少しは耐えられるような気がする。
この2年間で実感したことは、本屋という屋号を背負って自分にできるのは「たねをまくこと」でしかないこと、そこには常に本屋という営みの限界が表裏一体のものとしてあること、それを振り払うでも無視するでも限界突破するために大きな労力を割くでもなく、開き直って半分諦めながら可能性と限界を両輪に据えて根気強く「たねをまき続ける」しかない、ということだ。この連載を通してこれまでつらつら書いてきたことも、私からあなたへ手渡された「たね」でもあるのかもしれない。あなたはこの「たね」をどう受け取るだろうか。あなたやあなたの大切な人が少しでもこの社会で息をしやすくなるための酸素に、あるいは少しでも生きやすい社会へ舵をきるための櫂に、できるだけ広く遠く社会を見渡すための窓になることを願ってやまない。
岐阜での店舗営業を終了し、固定の場所に依存しない形で「たねをまく」ための実験/実践を続けるために、「たねをまくこと」という名前で小さな集まりを始めてみることにした。2025年6月に岐阜にて第1回目を開催した模様をメルマガにて配信している。
和田拓海(わだ・たくみ)
1997年兵庫県生まれ。2023年より岐阜市にて新刊書店「本屋メガホン」を主宰。
本屋メガホンについてはこちらから
*こちらの連載は「web灯台より」にて読むことも可能です。
*投げ銭していただけると執筆者と編集人に「あそぶかね」が入ります٩( ᐛ )و